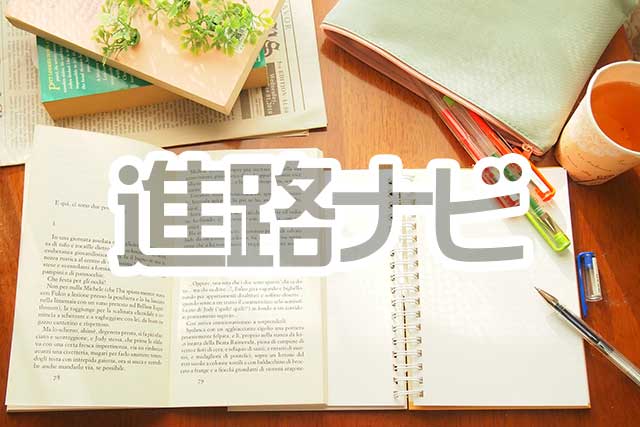- 大学
- 埼玉県
- 私立
十文字学園女子大学 先輩・先生方の声
先輩・先生の声
キミへのメッセージ
先輩からのメッセージ
-
栄養管理の知識を深め、 患者様の回復に役立ちたい
- 食物栄養学科 / 2019年3月卒業 / 丸木記念福祉 メディカルセンター【菅理栄養士】
- 松井 綾美さん

- 食物栄養学科 / 2019年3月卒業 / 丸木記念福祉 メディカルセンター【菅理栄養士】
- 松井 綾美さん
埼玉医科大学病院に管理栄養士として入職し、3年間の食数管理を中心とした厨房業務を経て、現在は回復期リハビリテーション病棟に勤務しています。在学中から興味があるスポーツ栄養に通ずる部分にもやりがいを感じながら、リハビリを考慮した栄養管理、入院・外来の実践可能な栄養指導、多職種連携で症例・評価に介入する摂食嚥下対策委員会の活動での中心的役割などを担っています。大学では、1 年次から先輩方のゼミに参加し、他大学や高校運動部
での栄養サポート活動を行ったり、管理栄養士の資格取得をめざし、自ら提案して行動する大切さを学びました。身近な商品を扱う「微生物学実験」の授業も面白くて印象的でした。これからも、より専門的な知識を深めて資格取得や学会発表に挑戦し、患者様からの信頼につなげたいと考えています。掲載年度:2024年
-
これからも向上心をもって、 貪欲に学び続けていきます
- 児童教育学科 / 2019年3月卒業 / 志木市立志木小学校
- 飯島 祐華さん

- 児童教育学科 / 2019年3月卒業 / 志木市立志木小学校
- 飯島 祐華さん
教員になり現在4 年目で、6 年生の担任を務めています。思春期や受験を控えた児童に接するにあたり、謙虚に、一人ひとりの気持ちに寄り添うことを大切にしています。職場でも先輩はもちろん、後輩の先生からも学ぶ姿勢で、様々なことを吸収し、自分も何かを提供できればという思いで、日々、精進しています。大学で学んだ指導案は、授業の基礎となるものです。大学で真剣に指導案に向きあったことが、今の授業づくりにつながっています。十文字の先生方は、地域の学校の授業研究で講師をされることも多く、“ 先生の先生”でもあります。そのような素晴らしい先生方の授業を受けていたことはとても贅沢な時間でした。卒業後も、相談にのってくださり、感謝の気持ちでいっぱいです。
掲載年度:2024年
-
子どもが施設を出た後も、 長く付き合いながら支えていきたい
- 人間福祉学科 / 2022年3月卒業 / 社会福祉法人錦華学院【児童指導員】
- 小野寺 瞳さん

- 人間福祉学科 / 2022年3月卒業 / 社会福祉法人錦華学院【児童指導員】
- 小野寺 瞳さん
本院で1年間勤務し、今年度からより家庭的な環境のグループホームで幅広い年齢の子どもの生活支援を行っています。食事作りや家事、長期休みには事前準備をしっかりして宿泊行事や遠出をするほか、児童相談所と連携し、保護者対応や子どもの支援にも取り組んでいます。実際に働いてみて、大学での学びを思い出す機会も多いです。特に、
児童養護施設で勤務されていた伊藤陽一先生の「社会的養護」の授業が活きており、年度目標を立てる際に使う自立支援計画の作成経験が役立ちました。保育士と社会福祉士の資格取得に向けた実習で実践経験も積んでいたため、落ち着いて現場に入れたのもよかったです。先輩方からのアドバイスも参考に、一人ひとりの成長や背景に対応できる引き出しを増やし、“お姉ちゃん”くらいの近い距離感で子どもに寄り添いながら、アフターサポートまでしっかり行っていきたいと思います。掲載年度:2024年
先生からのメッセージ
-
的確なスポーツ栄養マネジメントができる栄養士を育成するため、実践的な学修を展開
- 健康栄養学科 教授
- 村田 浩子先生

- 健康栄養学科 教授
- 村田 浩子さん
スポーツの現場を想定した実践的な研究を行っています。食事調査や消費エネルギー量の推定、そしてその結果に基づいた指導を繰り返し実施することで、どんな状況でも栄養士として的確な判断力を養います。また、対象はトップアスリートから老若男女まで多岐にわたるため、指導者やコーチ、保護者とのコミュニケーションの取り方や、子どもや高齢者アスリートの注意点など、細かな部分についても指導しています。健康栄養学科では、スポーツ栄養マネジメントを中心とした様々な授業が展開されています。
掲載年度:2020年
十文字学園女子大学の関連コンテンツ!
この学校を見ている人は、こちらも見ています
最近見た学校
関連キーワードを選択して学校を探す
おまかせ資料請求で
無料プレゼント


「どの学校を選べばいいかわからない…」「行きたい学校が決まらない…」そんな学校選びに迷っている高校生へ
「興味のある分野」「通学希望エリア」をえらぶだけで、進路アドバイザーがおすすめする学校の資料をお届けします(無料)!
「かんたん3STEP」で完結!
- 学校の種類と気になる分野・系統を選択
- 通学希望エリアを選択
- 送付先を入力
今なら人気のガイドブックを
無料プレゼント中!