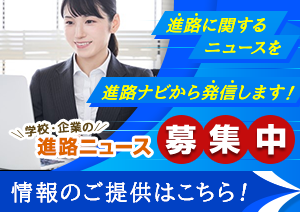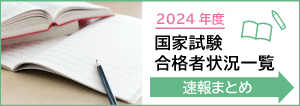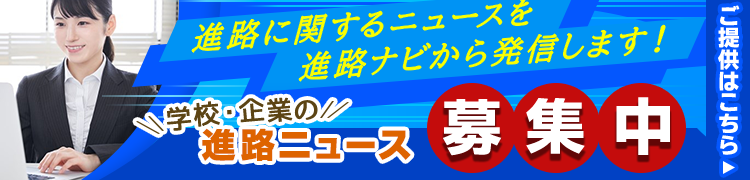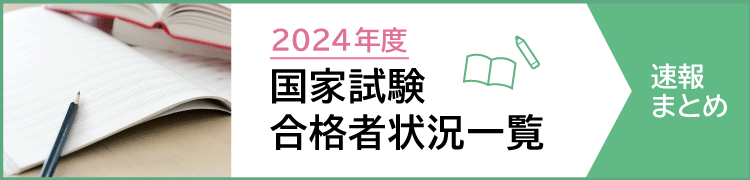「大学におけるキャリア支援の閑散期?」筆者・法政大学キャリアデザイン学部 教授 児美川孝一郎 更新日: 2025年4月26日
高校生のための進路ナビニュース
私立大学で教員をしている筆者にとって、
2月の中旬以降は、年間を通じてもっとも大学関連の業務が少なくなる時期である。
(※編注:本コラムは2月中~下旬に執筆いただきました)
秋学期の試験や採点、卒業論文や修士論文の審査、次年度の授業のシラバス作成、
一般入試の監督業務を終えると、目に見えて仕事が少なくなってくる。
逆に言えば、年に何度かしか訪れてくれない、自分自身の研究や執筆活動などに打ち込める時期になる。
今年もやっとこの時期を迎えることができたと安堵しているとき、
ふと職員はどうなのだろうという問いが頭をよぎった。
法人系の部署で働いている方々のことはわからないが、
学務系の部署の職員は、教員と同じなのではないか。
次年度に向けた準備等はあるとしても、そもそも学生がキャンパスに来ない時期なのだから。
とすれば、キャリアセンター等で働くキャリア系の職員は、どうだろう。
大学によっても事情は異なるかもしれない。
卒業を控えた4年生にそれなりの数の未内定者が存在するような大学であれば、
この時期でも4年生向けの懸命な就職支援をしているにちがいない。
また、近年では、大学の教育課程として海外インターンシップに取り組む大学もある。
そうした大学の場合には、学生が授業のないこの時期に海外のインターンシップ先に出かけていて、
諸々の対応に追われるといったケースもなくはないだろう。
では、そうした事情のない大学におけるキャリア系の職員は、
2月のこの時期は、普段と比較すれば、さすがに閑散期になるのだろうか。
日頃、忙しそうに立ち振る舞っている姿を見ているだけに、
そうであってほしいと思うのだが、はたしてどうか。
実際には、2月は3年生対象の冬のインターシップが真っ盛りの時期である。
このインターンシップを皮切りに、3月以降には会社説明会等も含めて、
3年生の就職活動が本格化していく。
もちろん、こうした学生の活動に大学がどこまで関与し、支援をするのかは、
大学によっても異なるだろう。しかし、2月以降が、
キャリア系の職員が安穏としていられる時期ではないことは確かだろう。
いったいいつから、こんなことになったのだろう。
就活の早期化、長期化、インターンシップ等を含めた多チャンネル化は、
学生生活を圧迫するだけではなく、大学職員の業務過多をも引き起こしていないだろうか。
【プロフィール】
教育学研究者。
1996年から法政大学に勤務。
2007年キャリアデザイン学部教授(現職)。
日本キャリアデザイン学会理事。
著書に、『高校教育の新しいかたち』(泉文堂)、
『キャリア教育のウソ』(ちくまプリマー新書)、
『夢があふれる社会に希望はあるか』(ベスト新書)等がある。