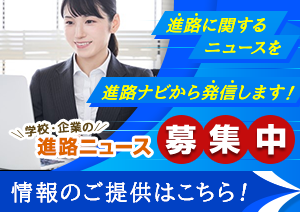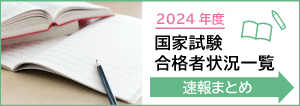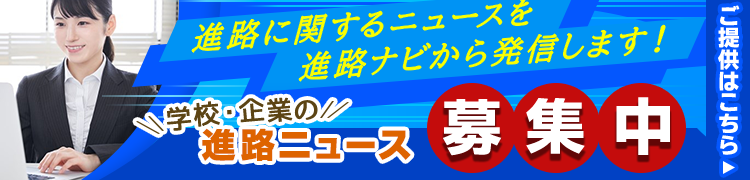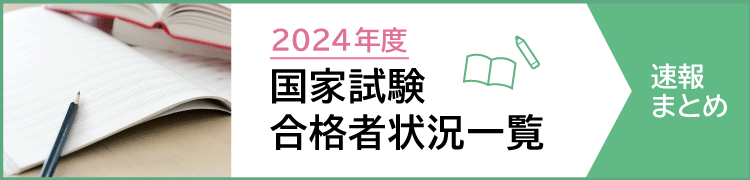гҖҢгӮӯгғЈгғӘгӮўеұ•жңӣгҒ®ең°еҹҹе·®гҖҚзӯҶиҖ…гғ»жі•ж”ҝеӨ§еӯҰгӮӯгғЈгғӘгӮўгғҮгӮ¶гӮӨгғіеӯҰйғЁгҖҖж•ҷжҺҲгҖҖе…җзҫҺе·қеӯқдёҖйғҺ жӣҙж–°ж—Ҙ: 2025е№ҙ4жңҲ19ж—Ҙ
й«ҳж Ўз”ҹгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®йҖІи·ҜгғҠгғ“гғӢгғҘгғјгӮ№
д»Ҡе№ҙгӮӮпј‘жңҲгҒ«жҲҗдәәгҒ®ж—ҘгӮ’иҝҺгҒҲгҒҹгҖӮ
еӨҡгҒҸгҒ®иҮӘжІ»дҪ“гҒҜгҖҒзҸҫеңЁгҒ§гӮӮ20жӯігӮ’еҜҫиұЎгҒ«гҒ—гҒҰгҖҒжҲҗдәәгҒ®ж—ҘгҒ«йӣҶгҒ„гӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮ2022е№ҙд»ҘйҷҚгҖҒгҒ“гҒ®еӣҪгҒ®жҲҗдәәе№ҙйҪўгҒҜ18жӯігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ§гҒҜгҖҒд»ҠгҒ©гҒҚгҒ®18жӯігҒҜгҖҒгҒ©гӮ“гҒӘж„ҸиӯҳгӮ„дҫЎеҖӨиҰігӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ
иҮӘжІ»дҪ“гҒҜгҖҒ18жӯігҒ«гҒҜгҒӮгҒҫгӮҠзӣ®гӮ’еҗ‘гҒ‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒ
ж—Ҙжң¬иІЎеӣЈгҒҜгҖҒ18жӯійҒёжҢҷжЁ©гҒ®жҲҗз«ӢеҫҢгҒ®2018е№ҙгҒӢгӮүгҖҒгҖҢ18жӯіж„ҸиӯҳиӘҝжҹ»гҖҚгӮ’з¶ҷз¶ҡзҡ„гҒ«е®ҹж–ҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
иӘҝжҹ»гҒҜгҒҷгҒ§гҒ«з¬¬67еӣһгӮ’ж•°гҒҲгҖҒ2025е№ҙгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүзҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҹжңҖж–°гҒ®иӘҝжҹ»гҒҜгҖҒ
дҫЎеҖӨиҰігғ»ж•ҷиӮІгӮ’гғҶгғјгғһгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгҒ®ең°еҹҹй–“жҜ”ијғгӮ’и©ҰгҒҝгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
е…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒеӨ§еӯҰйҖІеӯҰгҖҒиӮІгҒЈгҒҹиЎ—гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®и©•дҫЎгҖҒ
е°ҶжқҘиҮӘеҲҶгҒҢиӮІгҒЈгҒҹиЎ—гҒ§жҡ®гӮүгҒ—гҒҹгҒ„гҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹзӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒ
дёӯеӯҰеҚ’жҘӯжҷӮгҒ®еұ…дҪҸең°гҒ«еҹәгҒҘгҒҸйғҪйҒ“еәңзңҢеҲҘгҒ®еҲҶжһҗгҒЁгҖҒ
дёүеӨ§йғҪеёӮеңҸдёӯеҝғйғЁпјҸдёүеӨ§йғҪеёӮеңҸе‘ЁиҫәйғЁпјҸең°ж–№еңҸдёӯеҝғйғЁпјҸең°ж–№еңҸе‘ЁиҫәйғЁ
гҒЁгҒ„гҒҶпј”гҒӨгҒ®йғҪеёӮгӮҝгӮӨгғ—еҲҘгҒ®еҲҶжһҗгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
жіЁзӣ®гҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒ
пјҲпј‘пјүеӨ§еӯҰйҖІеӯҰзҺҮгҒҜгҖҒдёүеӨ§йғҪеёӮеңҸгҒҢең°ж–№еңҸгӮҲгӮҠгӮӮжңүж„ҸгҒ«й«ҳгҒ„гҖҒ
пјҲпј’пјүе°ҶжқҘгҖҒиҮӘеҲҶгҒҢиӮІгҒЈгҒҹиЎ—гҒ§жҡ®гӮүгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮӢиҖ…гҒҢеӨҡгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒ
гҖҖз”·еҘігҒЁгӮӮгҒ«гҖҒдёүеӨ§йғҪеёӮеңҸдёӯеҝғйғЁпјҲз”·жҖ§гҒ§гҒҜ43.4пј…пјүгҖҒ
гҖҖдёүеӨ§йғҪеёӮеңҸе‘ЁиҫәйғЁгҖҒең°ж–№еңҸдёӯеҝғйғЁгҖҒең°ж–№еңҸе‘ЁиҫәйғЁпјҲ26.7пј…пјүгҒ®й ҶгҒЁгҒӘгӮӢгҖҒ
пјҲпј“пјүгӮӯгғЈгғӘгӮўгғўгғҮгғ«гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҒһгҒҸгҒЁгҖҒең°ж–№еңҸгҒ®еҘіжҖ§гҒ®гҒҝгҒҢгҖҢдҝқиӯ·иҖ…гҖҚгӮ’жҢҷгҒ’гӮӢиҖ…гҒҢжңҖгӮӮеӨҡгҒҸгҖҒ
гҖҖд»–гҒҜгҖҢеҸӮиҖғгҒ«гҒӘгӮӢдәәгҒҜгҒ„гҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒӘгӮӢгҖҒ
пјҲпј”пјүиҮӘеҲҶгҒҢиӮІгҒЈгҒҹиЎ—гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҢе°ҶжқҘгҒ®йҒёжҠһиӮўгҒҢеӨҡгҒ„гҖҚгҒЁгҒҷгӮӢеӣһзӯ”гҒҜгҖҒ
гҖҖдёүеӨ§йғҪеёӮеңҸдёӯеҝғйғЁпјҲ80.1пј…пјүгҖҒдёүеӨ§йғҪеёӮеңҸе‘ЁиҫәйғЁгҖҒең°ж–№еңҸдёӯеҝғйғЁгҖҒең°ж–№еңҸе‘ЁиҫәйғЁпјҲ37.7пј…пјү
гҖҖгҒ®й ҶгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒгҒӢгҒӘгӮҠгҒ®й–ӢгҒҚгҒҢгҒӮгӮӢгҖҒ
гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹзөҗжһңгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
й«ҳж ЎгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮеӨ§еӯҰгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮгҖҒйҖІи·ҜжҢҮе°ҺгӮ„гӮӯгғЈгғӘгӮўж•ҷиӮІгҒ«жҗәгӮҸгӮӢж•ҷе“ЎгӮ„ж”ҜжҸҙиҖ…гҒҜгҖҒ
гҒ“гҒҶгҒ—гҒҹиӢҘиҖ…гҒҹгҒЎгҒ®гӮӯгғЈгғӘгӮўеұ•жңӣгҒ®ең°еҹҹе·®гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒгҒ©гҒҶиҖғгҒҲгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ
иӮҢж„ҹиҰҡгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜең°еҹҹе·®гӮ’иӘҚиӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶиҖ…гҒҢгҖҒеӨҡж•°жҙҫгҒӘгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҒ©гҒҶиёҸгҒҫгҒҲгҒҰгҖҒгӮӯгғЈгғӘгӮўж”ҜжҸҙгҒ®ж–№жі•гӮ„гҒӮгӮҠж–№гӮ’зө„гҒҝз«ӢгҒҰгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®йҖІи·ҜжҢҮе°ҺгӮ„гӮӯгғЈгғӘгӮўж•ҷиӮІгҒҜгҖҒгҒқгҒҶгҒЁж„ҸиӯҳгҒҜгҒ—гҒӘгҒ„гҒҫгҒҫгҒ«гҖҒ
гҒ„гҒӨгҒ®й–“гҒ«гҒӢеӨ§йғҪеёӮеңҸгҒЁгҒ„гҒҶз”ҹжҙ»з©әй–“гӮ’еүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҰзҗҶи«–еҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒҜгҒ“гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгҖӮ
гҒқгҒҶгҒ—гҒҹзӮ№гҒёгҒ®еҸҚзңҒгӮӮеҗ«гӮҒгҒҰгҖҒеӨ§гҒ„гҒ«иҖғгҒҲгҒ•гҒӣгӮүгӮҢгӮӢиӘҝжҹ»зөҗжһңгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҗгғ—гғӯгғ•гӮЈгғјгғ«гҖ‘
ж•ҷиӮІеӯҰз ”з©¶иҖ…гҖӮ
1996е№ҙгҒӢгӮүжі•ж”ҝеӨ§еӯҰгҒ«еӢӨеӢҷгҖӮ
2007е№ҙгӮӯгғЈгғӘгӮўгғҮгӮ¶гӮӨгғіеӯҰйғЁж•ҷжҺҲпјҲзҸҫиҒ·пјүгҖӮ
ж—Ҙжң¬гӮӯгғЈгғӘгӮўгғҮгӮ¶гӮӨгғіеӯҰдјҡзҗҶдәӢгҖӮ
и‘—жӣёгҒ«гҖҒгҖҺй«ҳж Ўж•ҷиӮІгҒ®ж–°гҒ—гҒ„гҒӢгҒҹгҒЎгҖҸпјҲжіүж–Үе ӮпјүгҖҒ
гҖҺгӮӯгғЈгғӘгӮўж•ҷиӮІгҒ®гӮҰгӮҪгҖҸпјҲгҒЎгҒҸгҒҫгғ—гғӘгғһгғјж–°жӣёпјүгҖҒ
гҖҺеӨўгҒҢгҒӮгҒөгӮҢгӮӢзӨҫдјҡгҒ«еёҢжңӣгҒҜгҒӮгӮӢгҒӢгҖҸпјҲгғҷгӮ№гғҲж–°жӣёпјүзӯүгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ