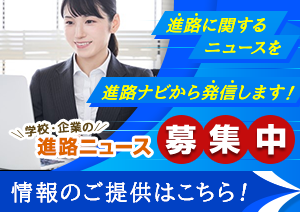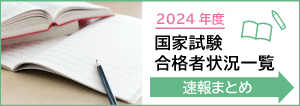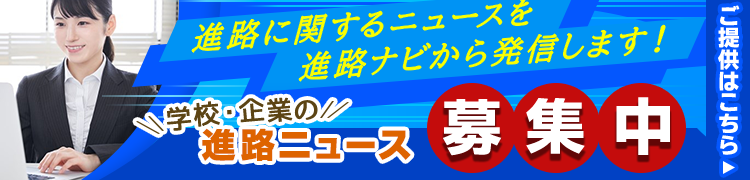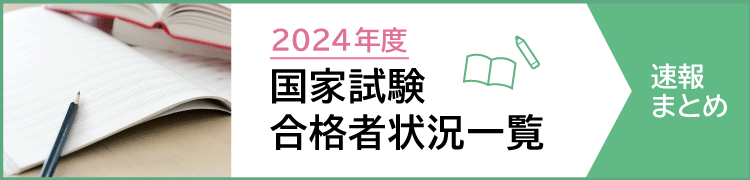「コンパクト+ネットワークによる学校づくり」筆者・葉養正明 更新日: 2025年4月16日
高校生のための進路ナビニュース
「コンパクト・シティ」は、少子化・人口減少が広域的に広がる状況のもと、
住民の暮らしの拠点を一定の地域エリアに集約しようとする都市政策であり、
暮らしに不可欠な公共施設等の持続、建替え施設の圧縮等による財政効率性の追求を背景にしている。
前回(※)触れたように、青森県八戸市や津軽半島、富山市などに導入事例が見られるが、
その導入についてはメリットもあればデメリットも指摘される。
(※参照:https://shinronavi.com/news/detail/1958 )
平成26年7月に国土交通省が公にした、
「国土のグランドデザイン2050~対流促進型国土の形成」では、
人口減少社会の構想として「コンパクト+ネットワーク」の考え方を提案している。
「+ネットワーク」を含まない「コンパクト・シティ」構想だけであると、
その内部に居住することを良しとしない住民が排除される恐れが生ずるが、
「コンパクト化」と「ネットワーク化」との組み合わせで考えていくと、
特定住民の社会的排除のリスクは乗り越えが可能である。
なお、コンパクト・シティのデメリットとしては、次の4項目があげられている。
●居住地域が限られてくる
●コンパクト・シティ化を希望しない住民もいる
●隣人トラブルなどの増加
●物価高の懸念
国土交通省などの都市政策では学校等の配置政策が触れられないことが多いが、
憲法上義務教育はすべての国民が享受する権利を有する。
そこで、人口減社会における都市政策としてコンパクト・シティを取り上げる際にも、
保育所・幼稚園などの乳幼児施設、小中学校の配置などに目配りした考察が必要になる。
小中学校を取り上げてみれば、学校教育法施行規則で12~18学級が適正規模とうたわれるからである。
「コンパクト・シティ」構想を前面に出すと、
青森県東通村のように1か所に小中学校、幼稚園等の集約を招くことになる。
学校の適正規模の厳格な維持のためには、
村全体の児童生徒数に照らすと、小中学校1校設置が妥当ということになるからである。
なお、現在の東通村では、小学校、中学校ともに各学年学級数は1または2学級である。
東通村学園の学校だよりには、長欠者、いじめ認知件数、学力状況などが、
全国や青森県内と対比してやや悪化している状況が示されている。
「コンパクト・シティ+ネットワーク」の構想の場合には、
「+ネットワーク」活用による「学びの多様化学校」開設などの可能性が生まれ、
学習の個別最適化という現学習指導要領にも適合的である。
東日本大震災被災地の場合にも、海沿いの平地の学校が軒並み津波に襲われた事例もあり、
児童生徒数が減少しても高台にあって防災拠点にできる学校を残していたら、という事例も見られた。
「コンパクト・シティ」と学校適正規模論の固い結合が
唯一の選択肢であるかどうか、検討の余地がある。
かつて、『学校のない社会 学校のある社会』
(叢書<編集代表・中内敏夫>『産育と教育の社会史』、1983年、新評論)
という本が著されたことがあった。
未来社会でも長期的に人口減少が続く可能性はあるものの、
「無学校村」など架空のものという観念そのものを疑ってかかるべき現実こそが「現代」なのかもしれない。
【プロフィール】
教育政策論、教育社会学専攻。大学教員として46年間過ごし、
現在は東京学芸大名誉教授、 国立教育政策研究所名誉所員。
千葉教育創造研究会(隔月1回会合)に40年以上参加し、
さまざまな世代の教職員と「教育のこれから」をテーマに探究を進めてきた。
また、「災害文化研究会」(岩手大学工学部が組織化)や
「縮小社会研究会」(京大工学部等が組織化)に所属し、
縮小社会や大震災のもとでの教育について研究を進めている。
地域復興などに際して教育が持つレジリエンス(回復力、弾性力)に関心を持つ。
<これまでの経歴や著書、論文等>
https://bunkyo.repo.nii.ac.jp/records/7687