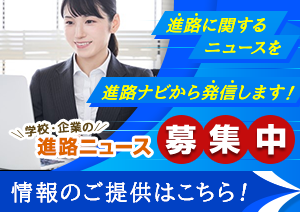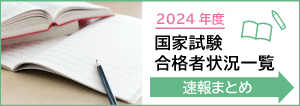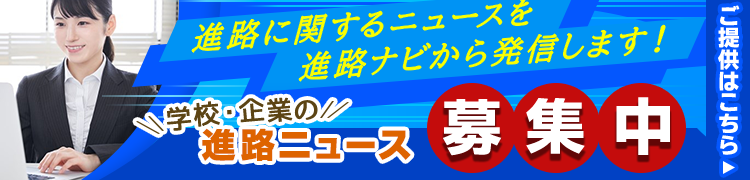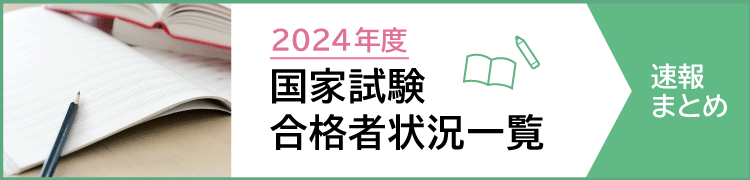「国立大学の授業料と財務の格差」筆者・桜美林大学総合研究機構 教授 小林雅之 更新日: 2025年3月26日
高校生のための進路ナビニュース
前回は同じ国立大学でも、大学間格差が拡大する可能性があることにふれた。
今回はさらに具体的に、東京大学と小樽商科大学を例に格差の現状をみていく。
少し煩わしい数字が続くが、格差の実態を多少なりとも正確に把握するためであるので、
辛抱して読み取っていただければ幸いである。
なお、これらの数字は、全て学生のために使われたわけではないことに留意する必要がある。
また、これらの数字は公表され入手できたものを使ったので、年度も異なるし、
本来はより精緻な計算が必要であり、あくまで概算であることをお断りする。
それでも格差の実態のおおよその傾向は知ることができる。
両大学には大きな差がある。まずその財務規模だ。
小樽商科大学の経常収益は約33億円。
東京大学の経常収益は約2,641億円(いずれも令和3年度)。
実に80倍以上の差がある。これは大学規模の差にもよる。
小樽商科大学は学士課程学生数2,226名、大学院院生数101名で合計約2千3百名(令和5年度)。
東京大学は学士課程学生数14,110名、大学院院生数15,016名で合計約2万9千人(令和6年度)。
学生数で約12倍の差がある。
これらの数字から学生ひとりあたりの経常収益についてみる。
小樽商科大学は約138万円、東京大学は約907万円と大きな差がある。
しかし、東京大学の経常収益には病院収入が約537億円と大きな割合を占めている。
病院の支出額と収入額はほぼ見合いなので、これを除くと、東京大学の経常収益は約2,100億円となる。
学生一人当たりでは、約720万円となる。差はかなり小さくなっているがそれでも約5倍の差がある。
もちろん、小樽商科大学は、その名の通り、商学部のみの単科大学であるのに対して、
東京大学は、理系の比率が高い。
学士課程学生数では約3割だが、院生では約6割で、合計の学生数に占める割合は、
約46%と半数に近い(ここでは、教養学部など理系と文系のある学部は除いている)。
こうした点を考慮しても小樽商科大学と東京大学には大きな差があるといえよう。
両者の収入に占める授業料の比率は大きく異なる。
授業料収入は、入学金と検定料を含めても東京大学は経常収入の1割以下であるのに対して、
小樽商科大学は約4割となっている。
このため授業料値上げの効果も大きく異なる。
東京大学ではあまり効果はないが、小樽商科大学では大きな効果がある。
このように具体的にみていくと国立大学の間でも大きな差があるのが明らかになる。
【プロフィール】
東京大学名誉教授、現・桜美林大学教授。
主な研究テーマは「高等教育論」「教育費負担」「学生支援」「学費」。
奨学金問題の第一人者として知られ、
『大学進学の機会』(東京大学出版会)、
『進学格差』(筑摩書房)など著書多数。