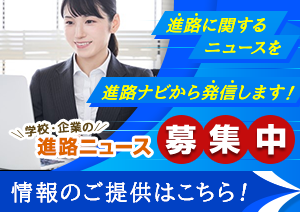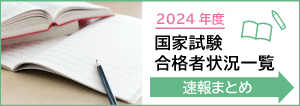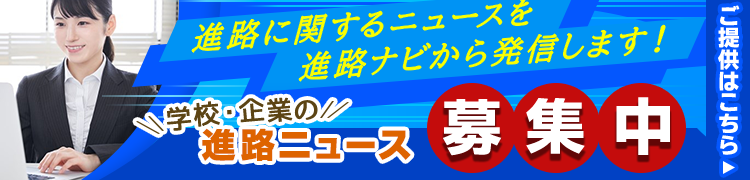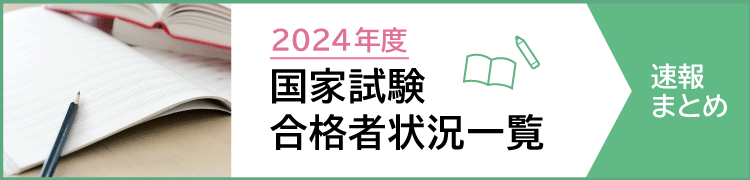гҖҢеӣҪз«ӢеӨ§еӯҰгҒ®иІЎж”ҝзҠ¶жіҒгҖҚзӯҶиҖ…гғ»жЎңзҫҺжһ—еӨ§еӯҰз·ҸеҗҲз ”з©¶ж©ҹж§ӢгҖҖж•ҷжҺҲгҖҖе°Ҹжһ—йӣ…д№Ӣ жӣҙж–°ж—Ҙ: 2025е№ҙ2жңҲ13ж—Ҙ
й«ҳж Ўз”ҹгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®йҖІи·ҜгғҠгғ“гғӢгғҘгғјгӮ№
жқұдә¬еӨ§еӯҰгҒ®жҺҲжҘӯж–ҷеҖӨдёҠгҒ’гҒ®иғҢжҷҜгҒ«гҒӮгӮӢеӣҪз«ӢеӨ§еӯҰгҒ®зҠ¶жіҒгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒе°‘гҒ—иҰӢгҒҰгҒ„гҒҚгҒҹгҒ„гҖӮ
еӣҪз«ӢеӨ§еӯҰгҒҜ2004е№ҙгҒ«жі•дәәеҢ–гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жҷӮгҖҒеӨ§еӯҰгҒ®йҒӢе–¶гҒ®иЈҒйҮҸгҒҢеӨ§е№…гҒ«жӢЎеӨ§гҒҷгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒжі•дәәеҢ–еүҚгҒ®еӣҪз«ӢеӨ§еӯҰгҒҜеӣҪгҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒ«гҒҜж–ҮйғЁз§‘еӯҰзңҒгҒ®ж–ҪиЁӯгҒ§гҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҖҒ
дәҲз®—гҒӘгҒ©гҒҜж–ҮйғЁз§‘еӯҰзңҒгҒЁеӣҪз«ӢеӨ§еӯҰгҒ®жҠҳиЎқгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒ
ж–ҮйғЁз§‘еӯҰзңҒгҒҢзҙ°йғЁгҒҫгҒ§еҺҹжЎҲгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҖҒеӣҪгҒ®дәҲз®—гҒЁгҒ—гҒҰеӣҪдјҡгҒ§еҜ©иӯ°гҖҒжұәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒжі•дәәеҢ–еҫҢгҒҜгҖҒеҗ„еӣҪз«ӢеӨ§еӯҰгҒҢдёӯжңҹиЁҲз”»еҺҹжЎҲгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҖҒ
ж–ҮйғЁз§‘еӯҰзңҒгҒҢгҒ“гӮҢгӮ’жұәе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒдәҲз®—гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜйҒӢе–¶иІ»дәӨд»ҳйҮ‘гҒЁгҒ„гҒҶеҪўгҒ§дёҖжӢ¬гҒ®иЈңеҠ©йҮ‘гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҢеӨ§еӯҰйҒӢе–¶гҒ®иЈҒйҮҸгҒ®жӢЎеӨ§гҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ“гҒ®жҷӮгҖҒйҒӢе–¶иІ»дәӨд»ҳйҮ‘гҒ«гҒҜгҖҒеҠ№зҺҮеҢ–дҝӮж•°гҒЁгҒ„гҒҶгҒ—гҒҸгҒҝгҒҢзө„гҒҝиҫјгҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜзӢ¬з«ӢиЎҢж”ҝжі•дәәгҒ«гҒӮгӮӢгҒ—гҒҸгҒҝгӮ’гҒқгҒ®гҒҫгҒҫз¶ҷжүҝгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеҗ„еӣҪз«ӢеӨ§еӯҰгҒҜжҜҺе№ҙпј‘гғ‘гғјгӮ»гғігғҲгҒҡгҒӨйҒӢе–¶иІ»дәӨд»ҳйҮ‘гҒҢжёӣе°‘гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҢгҖҢеҠ№зҺҮеҢ–гҖҚгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜ無駄гҒӘж”ҜеҮәгӮ’еүҠжёӣгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒ
иЈңеҠ©йҮ‘д»ҘеӨ–гҒ®еӨ–йғЁиіҮйҮ‘гӮ’еў—гӮ„гҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гҒ—гҒҸгҒҝгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒгӮӮгҒҶе°‘гҒ—иӨҮйӣ‘гҒӘиЁҲз®—ејҸгҒЁгҒӘгӮӢгҒҢгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҒӮгҒҲгҒҰеҚҳзҙ”еҢ–гҒ—гҒҰиӘ¬жҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
пј‘гғ‘гғјгӮ»гғігғҲгҒ®еүҠжёӣгҒӘгҒ©гҒҹгҒ„гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒеӨ§еӯҰгҒ®ж”ҜеҮәгҒ«гҒҜеүҠжёӣгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„еӣәе®ҡиІ»гӮӮеӨҡгҒ„гҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒж”ҜеҮәгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘеүІеҗҲгӮ’еҚ гӮҒгӮӢдәә件費гҒҜгҖҒеүҠжёӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮ
гҒ“гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®еӨ§еӯҰгҒ§гҒҜгҖҒе°Ӯд»»ж•ҷе“ЎгҒҢйҖҖиҒ·гҒ—гҒҹеҫҢгҖҒйқһеёёеӢӨи¬ӣеё«гҒ§д»ЈжӣҝгҒҷгӮӢгҒӘгҒ©иӢҰиӮүгҒ®зӯ–гӮ’гҒЁгҒЈгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒҶгҒ—гҒҹејҘзё«зӯ–гҒҜ20е№ҙгӮӮз¶ҡгҒ‘гӮҢгҒ°йҷҗз•ҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҢгҖҒ2024е№ҙпј–жңҲгҒ«еӣҪз«ӢеӨ§еӯҰеҚ”дјҡгҒҢгҖҢгӮӮгҒҶйҷҗз•ҢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеЈ°жҳҺгӮ’еҮәгҒ—гҒҹиғҢжҷҜгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒ
жҺҲжҘӯж–ҷеҖӨдёҠгҒ’гҒ®еӢ•гҒҚгҒ®еӨ§гҒҚгҒӘиӘҳеӣ гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гҒ®зөҗжһңгҖҒеӨ–йғЁиіҮйҮ‘гҒ®зҚІеҫ—гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеӨ§еӯҰй–“гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘж је·®гҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
еӨ–йғЁиіҮйҮ‘гҒ®зҚІеҫ—гҒҢйӣЈгҒ—гҒ„еӨ§еӯҰгҒҜжҺҲжҘӯж–ҷеҸҺе…ҘгҒ«дҫқеӯҳгҒҷгӮӢеүІеҗҲгҒ®й«ҳгҒ„еӨ§еӯҰгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒ®еӨ§еӯҰгҒ§гҒҜгҖҒйҒӢе–¶иІ»дәӨд»ҳйҮ‘гҒ®еүҠжёӣгҒҢгғңгғҮгӮЈгғ–гғӯгғјгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӨ§еӯҰгҒ®зөҢе–¶гӮ’ең§иҝ«гҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒгҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒҜеӨ§еӯҰй–“гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеӨ§еӯҰеҶ…гҒ®еӯҰйғЁй–“гҒ§гӮӮеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«гҒӮгҒҰгҒҜгҒҫгӮӢгҖӮ
гҖҗгғ—гғӯгғ•гӮЈгғјгғ«гҖ‘
жқұдә¬еӨ§еӯҰеҗҚиӘүж•ҷжҺҲгҖҒзҸҫгғ»жЎңзҫҺжһ—еӨ§еӯҰж•ҷжҺҲгҖӮ
дё»гҒӘз ”з©¶гғҶгғјгғһгҒҜгҖҢй«ҳзӯүж•ҷиӮІи«–гҖҚгҖҢж•ҷиӮІиІ»иІ жӢ…гҖҚгҖҢеӯҰз”ҹж”ҜжҸҙгҖҚгҖҢеӯҰиІ»гҖҚгҖӮ
еҘЁеӯҰйҮ‘е•ҸйЎҢгҒ®з¬¬дёҖдәәиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰзҹҘгӮүгӮҢгҖҒ
гҖҺеӨ§еӯҰйҖІеӯҰгҒ®ж©ҹдјҡгҖҸпјҲжқұдә¬еӨ§еӯҰеҮәзүҲдјҡпјүгҖҒ
гҖҺйҖІеӯҰж је·®гҖҸпјҲзӯ‘ж‘©жӣёжҲҝпјүгҒӘгҒ©и‘—жӣёеӨҡж•°гҖӮ