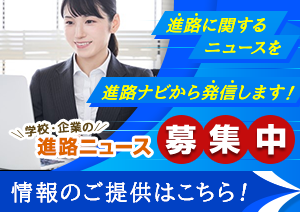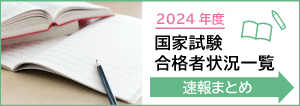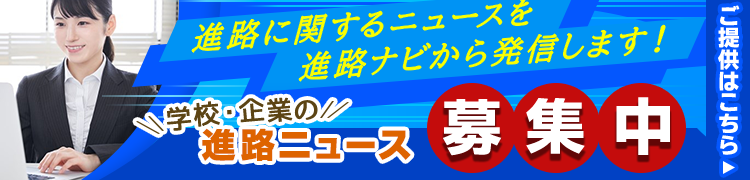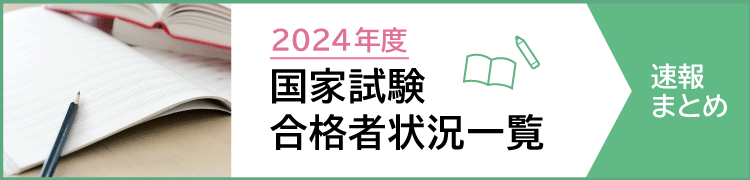「縮小社会の学校小規模化をどう乗り越え、可能性をどう生かすか その2」筆者・葉養正明 更新日: 2025年1月30日
高校生のための進路ナビニュース
10月に衆議院選挙が行われ国会の情勢は様変わりしたが、
我が国の少子高齢化の動向には大きな変化はない、というのが一般的な見方である。
合計特殊出生率が改善することがあっても、その効果が及ぶには数十年を要する、
というのが専門家筋の見方になっている。
ましてや現在は合計特殊出生率が低迷しており、長期的な人口減を避けることは難しい。
前回(※)は、人口減少が急激に進むある地域の小中併設校校長対象のヒアリング結果を紹介した。
(※参照:https://shinronavi.com/news/detail/1927 )
今回は、続編をお届けしよう。
「小中併設校の課題としてはどのような点をあげられるか」についてのヒアリング結果である。
(1)子どもと地域との親密なつながりは深い反面、人間関係の広がりに課題がある
「(児童生徒数が極めて少ない点は、)小中併設の課題のところになってくるんですが、
競争心がないといいますか、ずっと小さいころから同じ集団で、
お互いにお互いをわかっているので、その枠から出るというのには、
よほど私たちのほうで意図的に働きかけをしていく必要があると、そんなことも思っています。
小さい学校で、一村一小中ですので、村の方たちも、村人、議会の方ですとか、
村の役場の方や教育委員会の方たちに限らず、本当に村人たちが子どもたちをよく知っています。
それこそ、あの子のおじいちゃんは誰でおばあちゃんは誰で、
というところまで村人はよくわかっていますので、
そういう面では村が非常に学校に関心を持ってかかわってくれているという点も
こういう学校の利点かなというふうに思っています。」
(2)小規模化する学校では、教員のやりくりに難がある
「中学校の生徒数は今年度26人ですが、国基準の配当教員数は7で3学級です。
昨年までは特別支援を含めて4学級あったんですけれども、
3学級、4学級、いずれにしましても配当が7ということで、
……どうしても非免許申請をせざるを得ない状況にあります。
本校では、体育は教頭が免許を持っておりますので、
それから数学と技術の免許を持っている教員が1人いますので、
体育と技術についてはいいんですが、家庭科については非免申請をせざるを得ない。」
(3)多様な考え方や感じ方をぶつけ合う機会が乏しい
(4)部活動の持続に頭を悩ます
「中学校では子どもたちの意識の中に部活動というのが結構大きなウエートを占めるんですが、
部活動が維持できなくなってくるというのがあります。
本校ですと、今、男子は卓球部しかありません。
それから、女子はソフトテニス部しかありません。そして、男女共通で吹奏楽部があります。
ところが、こういう村にあっても、全員部活動に入るかというとそうではないです。
中には剣道ですとか、ことし初めて水泳の子が1人いるんですが、
多少遠い場所にあったとしても自分のやりたいことをやりたいとか、
あるいは社会体育で小学校のころからやってきた剣道で中体連も参加していきたいですとか、
そういう考えのお子さんもいますので、私はそれを尊重してあげようかなと思っています。」
(5)高校通学をどう保障するか
「それから、これは小規模校というよりは立地の問題なのですが、
高校の通学がやっぱり困難であるということがあります。
本校から通える学校、自宅から通学できる高校というのはM高校1校のみですので、
それ以外はアパートでひとり暮らしをするか、親戚がI市内にあれば出ていけるとか。」
学校小規模化は我が国全体の趨勢になっており、
「学校には適正規模がある」という観念に立つ限り地域社会からは学校が消えていく。
では、青森県津軽半島や富山市のようなコンパクトシティー構想で乗り切るしかないのか。
「選択と集中」原理を住民の故郷に適用しようとする発想である。
そこで、次回はこのコンパクトシティーを取り上げ考えてみることにしよう。
【プロフィール】
教育政策論、教育社会学専攻。大学教員として46年間過ごし、
現在は東京学芸大名誉教授、 国立教育政策研究所名誉所員。
「縮小社会研究会」(京大工学部等が組織)に所属し、
縮小社会下の教育について研究を進める。
大震災や戦乱などの社会変動のもとにおける教育復興と地域計画についても
関心を抱く。近年の論文等には、
「東日本大震災における宮古市の子どもの生活・学習環境意識の変化と
レジリエンスー縦断調査を通して」(『災害文化研究』第6号、2022年5月)、
単著、『人口減少社会の公立小中学校の設計
-東日本大震災からの教育復興の技術』(協同出版)、などがある。