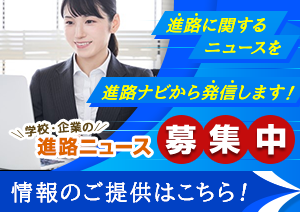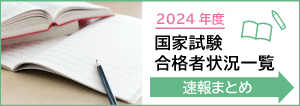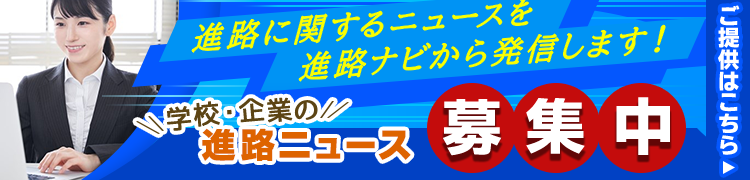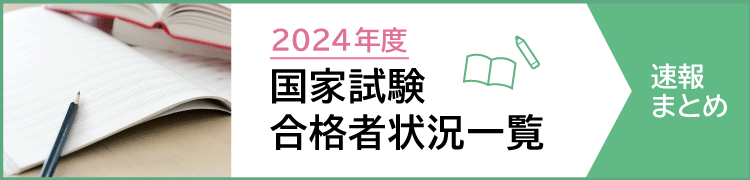「総合学科高校の変遷から今後の展望を考察する 1」筆者・日本大学商学部 准教授 玉川弘文 更新日: 2025年1月24日
高校生のための進路ナビニュース
平成2年度、私は定時制課程6年目の教員として、
教務部、教育課程を担当しながら、在籍管理や入試にもかかわっていた。
学期のはじめには全日制の中途退学者転編入募集があった。
定時制が受け入れなくては、中途退学者は増える一方だ。中卒者が増える。
そのため、「受検者は全員合格!?」
私の勤務する学校は荒れまくっていた。
定時制は勤労学生のための学校というイメージは、まったく無くなっていた。
平成2年度高等学校の中途退学者数は、
昭和57年度の調査開始以来、最高の123,529人、深刻な社会問題となっていた。
そのため、当時は教育改革・高校改革に国が積極的に取り組み、
「高校教育改革のパイオニア」として平成6年に総合学科が制度化、
日本の教育を牽引する役割を期待されていた。
それから30年。令和6年度都立高校全日制等志望予定(第1志望)の全日制総合学科は、
10校のうち5校の倍率が1.00以下である。他の道府県も同様であろう。
都立のチャレンジスクール(総合学科・定時制)は、
主に小・中学校での不登校の経験や高校での中途退学の経験により、
これまで能力や適性を十分に生かしきれなかった生徒が、自分の目標を見つけ、
それに向かってチャレンジする高校で、6校のうち2校が倍率1.00以下である。
私は総合学科高校を3校経験した。
2校は開設要員の教務主任として学校の全ての業務にかかわりつくり上げた。
1校は校長として学校経営に奮闘した。
その経験を踏まえ、次回からは総合学科高校の変遷から今後の展望を考察する。
【プロフィール】
日本大学商学部准教授
1985年より東京都立高校に勤務
北地区チャレンジスクール(現・桐ヶ丘高等学校)開設準備室 教諭、
北地区総合学科高等学校(現・王子総合高等学校)開設準備室 主幹教諭、
晴海総合高等学校 校長 等を経て、2023年より現職