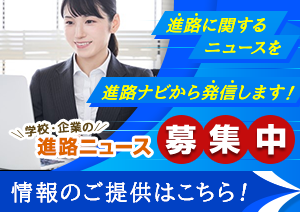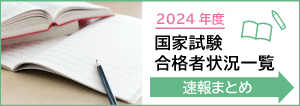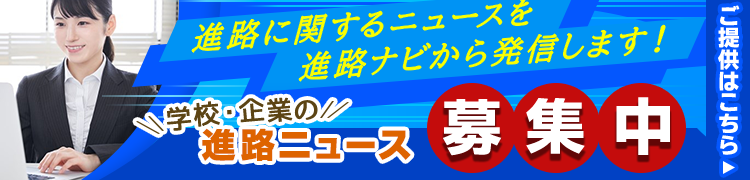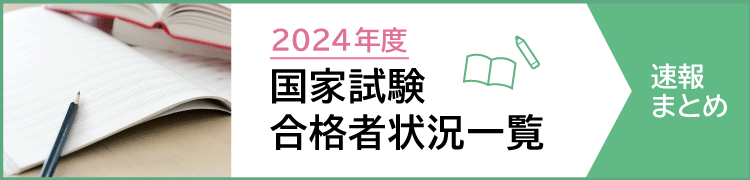「オンラインネットワークと社会的孤立」筆者・葉養正明 更新日: 2024年5月25日
高校生のための進路ナビニュース
定常型社会は人口減を伴うために、全国の人口密度の平均値は低下するが、
それ以上にインパクトが大きいのは人口密度がもともと小さい地域での人口密度の落ち込みである。
人口減少の専門家筋の分析を見ると、我が国の人口減は、
各地一律ではなくもともと人口密度の小さい地域ほど減少幅は大きい、とされる。
本稿で離島やへき地、中山間地の少子化・人口減少に注目する理由である。
ここ数回の小論で、
少子化人口減の厳しい地域でのオンラインネットワーク構築について取り上げているが、
オンラインネットワークは子ども同士、子ども・教師間、学校・地域間等での
対面的接触を必要条件と考えないことで地理的なハンディを乗り越えることができる、
という大きな長所を持っている。
では、オンラインネットワークは現下の社会で課題として浮上している、
「社会的孤立・孤独」の問題にどのようなかかわりを持つことになるのだろうか。
ここでは「社会的孤立」に限定して考えることにしよう。
この分野の先端的研究者である阿部彩氏(※)は、
「社会的孤立」に関する既存研究を整理し、その系統を3つに分類している。
(※阿部彩「包摂社会の中の社会的孤立―他県からの移住者に注目して―」
(社会科学研究65巻<2014>1号) https://doi.org/10.34607/jssiss.65.1_13 )
(1)一つ目の系統は、社会関係資本(ソーシャルキャピタル)の研究分野であり、
個人レベルおよび地域レベルの社会関係資本を分析しており、
社会的孤立は社会関係資本の欠如と理解されている。
(2)もう一つの系統は貧困研究の流れを組むものであり、
経済的困窮と人間関係や社会との結びつきの欠如が密接に関係しているものであるところから、
貧困をより広い概念である社会的排除と理解し、
人間関係の希薄さや社会サポートの欠如を社会的排除の一つの側面としてとらえている。
(3)最後の系統は、社会的孤立そのものを研究対象としている研究分野であり、
単独世帯や孤立死の増加といった社会的背景から社会的孤立の分析を行っている。
阿部氏は、既往の研究は、
社会的孤立を人間関係、ソーシャルネットワークの欠如としている点が共通している、とし、
「社会的孤立」は、社会的参加、社会的交流、社会的サポートという3つの概念に集約できるとする。
以上の阿部氏の整理に基づくと、
上述した少子化人口減地域でのオンラインネットワークは、
どのような可能性を持つか、「社会的孤立」克服などとどうかかわるか、という問いは、
バーチャルな社会では子どもの「社会的参加」、「社会的交流」、「社会的サポート」は
どう機能するか、という問いにかかわることになる。
イギリスなどの先行例を踏まえ、
国会でようやく制定された「孤独・孤立対策推進法」(令和5年5月)に見るように、
「社会的孤独」も「社会的孤立」も我が国ではこれからの課題に属する面が大きい。
ましてやオンラインネットワークが子どもの「社会的孤立」にどう寄与するかについては、
体系的に論ずるには研究不足である。しかし、子どもの世界では
不登校の激増などひきこもりの現象が拡大しつつある。
Covid-19の蔓延の下、子どもの学習を保障する手段としてオンラインネットワークが広がった、
という経験を引き合いに出しての思いであるが、バーチャルな空間は、
対面性のネットワークを挟まないでは人間教育には不十分という。
そのようなハイブリッド型のコミュニティのつくり方を模索するしかないのだろう。
それは、小中高大すべての段階の教員が共通に感じ取ったことだったのではないか。
【プロフィール】
教育政策論、教育社会学専攻。
大学教員として46年間過ごし、
現在は東京学芸大名誉教授、国立教育政策研究所名誉所員。
近年は、少子化・人口減少、大震災などの社会変動のもとにおける
学校システムのあり方を主テーマにしている。
特に、2050年ころの離島、へき地、中山間地の学校設置区域制度や
義務教育拠点の持続の方法などに関心を抱いている。