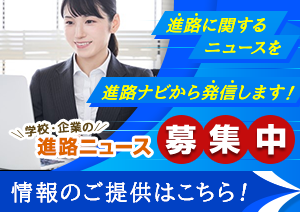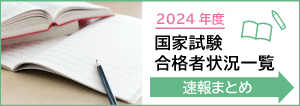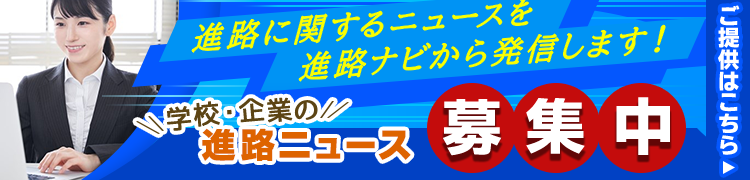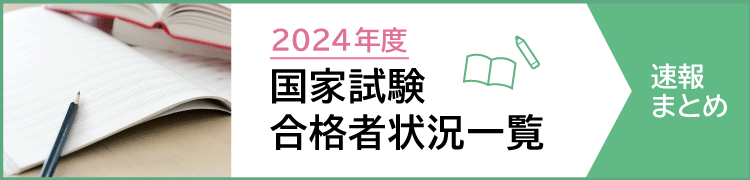гҖҢеӯҰзҙҡгҒҘгҒҸгӮҠгӮ’и»ҢйҒ“гҒ«гҒ®гҒӣгӮӢгҖҚзӯҶиҖ…гғ»дјҡжҙҘеӨ§еӯҰж–ҮеҢ–з ”з©¶гӮ»гғігӮҝгғјгҖҖж•ҷжҺҲгҖҖиӢ…й–“жҫӨеӢҮдәә жӣҙж–°ж—Ҙ: 2024е№ҙ5жңҲ24ж—Ҙ
й«ҳж Ўз”ҹгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®йҖІи·ҜгғҠгғ“гғӢгғҘгғјгӮ№
гҒӮгҒЈгҒЁгҒ„гҒҶй–“гҒ«пј§пј·гҒҢзөӮгӮҸгӮҠгҖҒж–°з·‘гҒ®гҒҫгҒ¶гҒ—гҒ„еӯЈзҜҖгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®еӯЈзҜҖгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒж°—жҢҒгҒЎгӮӮжҳҺгӮӢгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒеӯҰзҙҡгҒҘгҒҸгӮҠгҒ§гӮӮгҒӨгҒҺгҒ®дёҖжӯ©гӮ’иёҸгҒҝеҮәгҒ—гҒҹгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ•гҒҰгҖҒпј”жңҲгҒ®еӯҰзҙҡйӣҶеӣЈгҒҘгҒҸгӮҠгҒҜй ҶиӘҝгҒ«йҖІгӮ“гҒ гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
гғқгӮӨгғігғҲгҒҜе°‘гҒ—еј·гӮҒгҒ®гғӘгғјгғҖгғјгӮ·гғғгғ—пјҲгҖҢж•ҷзӨәзҡ„гғӘгғјгғҖгғјгӮ·гғғгғ—гҖҚпјүгҒ§гҖҒ
з”ҹеҫ’гҒ«иЎҢеӢ•гҒ®д»•ж–№гӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«иЎҢеӢ•гҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҢгҒҶгҒҫгҒҸгҒ§гҒҚгҒҹеӯҰзҙҡгҒ§гҒҜгҖҒз”ҹеҫ’гҒҹгҒЎгҒ«еӯҰж Ўз”ҹжҙ»гӮ’гҒҶгҒҫгҒҸйҒҺгҒ”гҒҷгҒҹгӮҒгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘиЎҢеӢ•гҒҢе®ҡзқҖгҒ—гҒҰгҖҒ
еӯҰзҙҡгҒ«жҳҺгӮӢгҒ„йӣ°еӣІж°—гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒз”ҹеҫ’й–“гҒ®й–ўдҝӮжҖ§гҒҢиүҜгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ§гҒҜгҖҒпј•жңҲгҒ«з•ҷж„ҸгҒҷгӮӢгғқгӮӨгғігғҲгҒҜдҪ•гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҢиӘ¬еҫ—зҡ„гҒӘгғӘгғјгғҖгғјгӮ·гғғгғ—гҖҚгҒ§з”ҹеҫ’гҒ«иЎҢеӢ•гҒ®ж„Ҹе‘ігӮ’дјқгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢиӘ¬еҫ—зҡ„гҒӘгғӘгғјгғҖгғјгӮ·гғғгғ—гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒ
гҒӘгҒңгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиЎҢеӢ•гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶиЎҢеӢ•гҒ®ж„Ҹе‘ігӮ’иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒгӮ„гӮүгҒӣгӮүгӮҢгӮӢиЎҢеӢ•гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒ
иҮӘеҲҶгӮӮзҙҚеҫ—гҒ—гҒҰиЎҢеӢ•гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮҲгӮҠгӮ№гғ гғјгӮәгҒӘиЎҢеӢ•гҒ®еҪўжҲҗгҒЁз¶ӯжҢҒгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒеӯҰзҙҡжӢ…д»»гҒ«гҒҜгҖҒпј”жңҲгҒЁеҗҢгҒҳгғӘгғјгғҖгғјгӮ·гғғгғ—гӮ’з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒ
з”ҹеҫ’гҒ®зҠ¶жіҒгҒ«еҜҫеҝңгҒ—гҒҹгғӘгғјгғҖгғјгӮ·гғғгғ—гҒ«еӨүгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
дёҖж–№гҖҒпј§пј·жҳҺгҒ‘гҒ«гҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢвҖңеӯҰзҙҡеҙ©еЈҠвҖқгҒ®зҠ¶жіҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹеӯҰзҙҡгҒҢгҒӮгӮӢгҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгҒ®еӯҰзҙҡгҒ§гҒҜгҖҒеӯҰзҙҡжӢ…д»»гҒҢз”ҹеҫ’гҒ®иҮӘдё»жҖ§гӮ’еӨ§дәӢгҒ«гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚзӣ®гҒ§гҖҒ
иҮӘз”ұгӮ’иЁұгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
иҮӘдё»жҖ§гӮ’еӨ§дәӢгҒ«гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁиҒһгҒ“гҒҲгҒҜгҒ„гҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒвҖңиҮӘз”ұгҒҜдёҚиҮӘз”ұвҖқгҒЁгӮӮиЁҖгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жңҖеҲқгҒҜж–№еҗ‘жҖ§гҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҖҒгҒқгҒ®ж–№еҗ‘гҒ«иғҢдёӯгӮ’жҠјгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮӢгҒ»гҒҶгҒҢжӯ©гҒҝгӮ„гҒҷгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҢгҒӘгҒ„гҒЁгҖҒгҒ©гҒЎгӮүгҒ«еҗ‘гҒӢгҒҶгҒӢгҒҢгӮҸгҒӢгӮүгҒҡгҖҒдёҖжӯ©гҒҢиёҸгҒҝеҮәгҒӣгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒҶгҒӘгӮӢгҒЁдёҚе®үгҒҢй«ҳгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒж„Ҹж¬ІгҒҢжёӣйҖҖгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒгғҚгӮ¬гғҶгӮЈгғ–гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮеҲәжҝҖгӮ’жұӮгӮҒгӮӢеҝғзҗҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҢдёҚйҒ©еҲҮгҒӘиЎҢеӢ•гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒеӯҰзҙҡеҶ…гҒ«е®үе…Ёгғ»е®үеҝғгҒҢзўәдҝқгҒ•гӮҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«гҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶзҠ¶ж…ӢгҒҢз¶ҡгҒҸгҒЁгҖҒеӯҰзҙҡгҒҢйӣҶеӣЈгҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—гҒӘгҒ„еӯҰзҙҡеҙ©еЈҠгҒҢиө·гҒ“гӮӢгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
иЎҢеӢ•ж§ҳејҸгҒҢж•ҙгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„еӯҰзҙҡгҒ§йҒ©еҲҮгҒӘиЎҢеӢ•гӮ’е®ҡзқҖгҒ•гҒӣгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒпј•жңҲдёӯж—¬гҒҢгҒҺгӮҠгҒҺгӮҠгҒ®жңҹйҷҗгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮ№гӮҝгғјгғҲгҒ«жҲ»гҒЈгҒҰгҖҒж•ҷзӨәзҡ„гҒӘгғӘгғјгғҖгғјгӮ·гғғгғ—гҒ§еӯҰзҙҡгҒҘгҒҸгӮҠгӮ’гӮ„гӮҠзӣҙгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
жңЁгҖ…гҒ®й–“гҒӢгӮүгӮӮгӮҢгӮӢгӮӯгғ©гӮӯгғ©гҒЁгҒ—гҒҹијқгҒҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘз”ҹеҫ’гҒ®з¬‘йЎ”гҒҢиҰӢгӮүгӮҢгӮӢеӯҰзҙҡгҒ«гҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҗгғ—гғӯгғ•гӮЈгғјгғ«гҖ‘
2015е№ҙгҒӢгӮүзҸҫиҒ·
е°Ӯй–Җй ҳеҹҹгҒҜгҖҢж•ҷиӮІеӯҰгҖҚгҖҢж•ҷиӮІгӮ«гӮҰгғігӮ»гғӘгғігӮ°еҝғзҗҶеӯҰгҖҚ
з ”з©¶гғҶгғјгғһгҒҜж•ҷиӮІеӣ°йӣЈж ЎгҒ§гҒ®ж”ҜжҸҙ